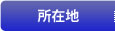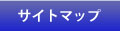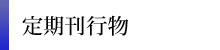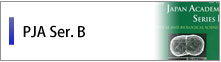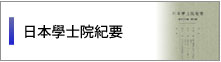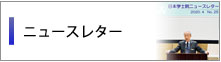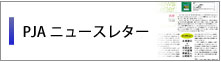日本学士院学術奨励賞の受賞者決定について
日本学士院は、優れた研究成果をあげ、今後の活躍が特に期待される若手研究者6名に対して、第8回(平成23年度)日本学士院学術奨励賞を授与することを決定しましたので、お知らせいたします。
| 氏名 | 市 大樹 (いち ひろき) |  |
|---|---|---|
| 生年月 | 昭和46年6月(40歳) | |
| 現職 | 大阪大学大学院文学研究科 准教授 | |
| 専門分野 | 日本古代史 | |
| 研究課題 | 日本古代の木簡と交通制度 | |
| 選考理由 | 現在、飛鳥木簡は約15,000点、藤原宮木簡は約16,000点、藤原京木簡は約14,000点の発見があり、七~八世紀初頭における生の資料として貴重ではあるが、木簡の一点一点から得られる文字情報は極めて零細で限定的なものであると言わざるを得ません。 |
|
| 氏名 | 高井 研 (たかい けん) |  |
|---|---|---|
| 生年月 | 昭和44年12月(42歳) | |
| 現職 | 海洋研究開発機構海洋・極限環境生物圏領域 プログラムディレクター |
|
| 専門分野 | 地球生物学 | |
| 研究課題 | 極限環境微生物の探索と生態系駆動原理の解明、および地球―生命初期進化研究への展開 |
|
| 選考理由 | 高井 研氏は、深海熱水域や地下・海底下などの極限環境における微生物の調査を行い、従来の常識を覆す極めて多様な微生物集団が生息すること、始原的な微生物が未分離のまま存在することを発見しました。そして、これらの微生物の生態系の規模や群集構造が、地球内部から熱水によって供給される還元化学エネルギーの種類と量によって決定づけられ、マグマ活動やプレートテクトニクスといった地質学的条件によって影響されることを明らかにしました。また、環境再現による培養法を開発し、多くの極限環境に生息する生物の培養に成功しました。最近では、122ºCで生育する微生物を発見し生命の最高増殖可能限界を更新しています。さらに、地球における生命の誕生と初期進化を説明するため、「地質-生命相互作用リンケージ」という概念を提唱するなど、生命科学、地球科学、化学にまたがる壮大な分野融合的研究を展開しており、本分野での指導的役割が高く評価されます。 |
|
| 氏名 | 田中 貴浩 (たなか たかひろ) |  |
|---|---|---|
| 生年月 | 昭和43年2月(44歳) | |
| 現職 | 京都大学基礎物理学研究所 教授 |
|
| 専門分野 | 相対論、宇宙論 | |
| 研究課題 | ブレーン重力の研究 | |
| 選考理由 | 田中貴浩氏は、ブレーン世界モデルにおける重力の振る舞いに関して数々の先駆的・系統的な研究を行い、国際的に評価の高い業績をあげてきました。その一例は、われわれの3+1次元世界がより高次元の時空中の3次元膜であるとするモデルに基づいて、ブレーン(膜)の曲がりの影響を含めた摂動計算を簡便に行う方法を開発し、アインシュタイン理論からのずれが重力ポテンシャルの補正項として現れることを示したことです。また、ブレーン宇宙は4次元アインシュタイン重力+強結合共形場理論の系と同等であるという仮説をブレーン上のブラックホールに適用すると、静的なブラックホール解は存在しないという予想を発表して活発な論議を巻き起こしました。一方、重力波についても、連星の一方がブラックホールである場合にもう一方の小質量天体が受ける重力的反作用力の基礎方程式を導き、連星の合体から発生する重力波のテンプレートを作成して観測計画の立案に貢献しています。 |
|
| 氏名 | 泊 幸秀 (とまり ゆきひで) |  |
|---|---|---|
| 生年月 | 昭和50年6月(36歳) | |
| 現職 | 東京大学分子細胞生物学研究所 准教授 東京大学大学院新領域創成科学研究科 准教授 |
|
| 専門分野 | RNA | |
| 研究課題 | 小分子 RNA がはたらく分子基盤の解明とその応用 | |
| 選考理由 | RNA が触媒機能を持つことの解明以来、RNA がmRNA としてタンパクの一次構造をコードしている以外に多くの機能を持つことが知られてきました。近年特に注目を集めているのは、小分子のRNA が生体機能の制御に複雑に関わっている点であり、現在最も活発に研究が進められ、発展中の分野です。小分子RNA の機能として、 mRNA によるタンパク質合成を、RISC (RNA-induced silencing complex) と呼ばれる複合体を介して制御するという役割が知られています。泊 幸秀氏は RISCに焦点を絞り、その形成過程や機能を解析し、RISCの核となる因子であるArgonauteタンパク質の機能の違いを明らかにすることなどを通して、タンパク質合成を小分子RNAが抑制する機構を見事に整理しました。また、RNA 干渉複合体の形成には分子シャペロンによる Argonaute タンパク質のダイナミックな構造変化が必要であることを示し、それまでの概念を覆しました。これら一連の研究は、将来特定の mRNAによるタンパク質合成を人工的に制御する可能性を示唆し、医薬への応用も期待されます。激烈な競争の渦中にあるこの分野において、泊氏の研究は世界的にも高い評価を得ています。 |
|
| 氏名 | 西村 栄美 (にしむら えみ) |  |
|---|---|---|
| 生年月 | 昭和43年11月(43歳) | |
| 現職 | 東京医科歯科大学難治疾患研究所 教授 | |
| 専門分野 | 幹細胞生物学、再生医学、皮膚病理学、老化生物学 | |
| 研究課題 | 色素幹細胞の同定、および維持制御と毛髪老化のメカニズムの解明 | |
| 選考理由 | 組織幹細胞の維持機構の解明は現代生命科学における重要課題の一つです。西村栄美氏は、マウスの毛にメラニン色素を送り込む色素細胞について研究し、その幹細胞を世界に先駆け同定、そして、この細胞を取り巻く環境(ニッチ)が、幹細胞の運命を制御することを明らかにしました。次いで、色素幹細胞に隣接する毛包幹細胞がニッチとして働き、この細胞が合成するTGFβが色素幹細胞の維持のために必要であること、最近では、毛包幹細胞が発現するコラーゲンXVIIが、毛包幹細胞だけでなく色素幹細胞の維持にも必要であることを明らかにしています。さらに、幹細胞維持機構の異常によって色素細胞が不足し、これが白髪化を引き起こすこと、また、色素幹細胞におけるDNA損傷が細胞の自己複製機能を抑制し、老化における白髪化の原因となることを示唆しています。以上、色素幹細胞の維持機構から白髪化の仕組みに至るまで数々の重要な新知見をもたらし、オリジナリティの高い研究であると評価されます。 |
|
| 氏名 | 平田 聡 (ひらた さとし) |  |
|---|---|---|
| 生年月 | 昭和48年6月(38歳) |
|
| 現職 | 京都大学霊長類研究所 特定准教授 |
|
| 専門分野 | 比較認知科学 | |
| 研究課題 | ヒトとチンパンジーの比較認知研究による社会的知性の進化的起源の解明 | |
| 選考理由 | 平田 聡氏は、チンパンジーの協力行動を実験的に検討し、他者の行為を見ることで学習の効率性を向上させることを見出しましたが、他方ではヒトのように真の模倣はおこなわれず、またヒトのようにアイコンタクトや合図を送るなどの積極的・明示的なコミュニケーションはみられないことをも示しました。これはヒトの相互協力の起源を考察するうえで貴重な発見です。さらに同実験においては、国際的に平田の装置として知られる巧妙な装置を工夫して、信頼性の高い結果をえています。これが平田氏の主たる研究業績ですが、その他にも普通は困難な脳波の観察をとおして、顔・自己名の認知におけるヒトとの種差を見出すなど、多くの独創的研究をおこない、過半の成果は一流の国際学術雑誌に掲載され、ひろく引用もされています。 |
|